■親の愛情が平等ではないのは当然!? 専門家「遺伝子が影響している」
う~ん・・・子どもへの愛情の差があるって言われてもねぇ。
まず、子どもが2人以上いないと、子どもにエコひいきしているかどうかもわからないですよね。
あと、親子の相性には、性別もかかわってくるでしょう。
やはり父親は、男の子と話が合いやすいですし、母親は女の子のほうが付き合いやすいものですわな、基本的には。
わたしは子どもが3人いるので、子どもの個性がわかりやすい環境ではあります。
子ども1人の家庭では、子どもに性格的な特徴があっても、子どもとはそんなものなのか、それともその子の個性なのか、わかりにくいもんなんですよね。
子どもは両親の遺伝子を半分ずつ受け継いでいるらしいですが、どの部分の遺伝子をどちらの親から受け継いだのかはそれぞれ違います。外見上は父親に似ていても、性格は母親に似ていたりするのはそのためですね。
うちの子どもたちも、3人それぞれまったく個性が違います。「一番自分に似ている子は誰か?」と聞かれたら、ちょっと答えに窮するなぁ。
それぞれ、この特性は自分の遺伝だな、と思える部分はあります。ただ、それもあちこちにすこしずつ分散しているんですよね。
うちは上から女、男、女の順番で、男の子は小学4年ですが、野球に興味が好きだったりするので、やはり一番話が合うのは男の子になります。
それが、一番愛情をかけている、ということなんですかね。それが遺伝子の影響?う~ん、ちょっとピンとこないな。
今はどの子どもも一人前になれるようにと、躾や教えることが多いので、それぞれ同じくらい注意を払っているつもりですけどね。
成人するくらいになると、親子間にも相性が出てくるのかもしれません。ただ、そこで自分に似ている子どもが一番かわいくなる、のかな?というと、それはどうなんだろう、と思う。
だいたい人間って「自分に似ている人間」のことを好きなんでしょうか。だったらクローン技術で自分とまったく同じ遺伝子の子どもを作れるのなら、その自分のコピー人間がすごくいとおしくなるってことですかね。
まあともかく、「自分に似てる」と言っても、性格と外見と2通りあるし、どの子どもが一番自分に似ているのかは、判別が難しい問題ですよ。
それに愛情の平等性は、性別や兄弟の人数などいろんな環境によって違ってくるので、医学的に親の愛情の平等性に遺伝子の影響があるにしても、現実で「自分に似ている子を優遇している」とわかる場面はあんまりないんじゃないですかね。

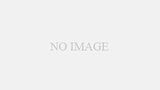
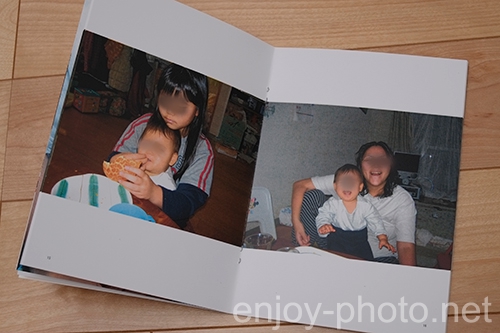
コメント