子の親であればたいていは、子どもの「集中力がない」とか「学力が上がらない」ということで悩んでいます。
親は子どもの学力を上げるために「厳しく指導する」「塾通いさせる」というふうに、子どもへの圧力を増やしてしまいがちです。
しかし、子どもの学力を上げるためには「子どもたちのやる気」や「勉強時間」といったことの前に、もっと子どもたちの学力に差がつく要因があります。
子どもの学力を上げるために必要なこと
百マス計算で有名な蔭山さんが9年前に出した本です。
特別な勉強法でも書かれているのか?という予想を裏切り、「子どもの学力を上げるためには、基本的な生活習慣がとても大切」という主張がなされています。
確実に子どもの学力を上昇させる方法は次の3つです。
早寝して十分な睡眠をとる
広島県下の小学5年生、約二万七千人について2004年におこなった調査です。
睡眠時間が四時間台の子どもたちは国語の平均点が53.1点、算数が56.7点というふうに50点台しかとれません。
ところが睡眠時間が5時間台に増えただけで64.7点、69.1点というふうに、早速10点以上も平均点が上がってきます。
そして6時間7時間となるにつれて、テストの平均点が上がってくる。
7時間、8時間、9時間だと、だいたい70点は取れるぐらいに成績が安定してくるのです。
統計では「早く寝る子ほど学力は高い」のです。
今では小学生でも0時すぎまで起きている子どもも珍しくありません。
「早寝早起き」がよいことだということは昔から言われて来ましたが、倫理道徳の話だけではなく、上記のように統計的にも効果が確認できていることなのです。
成長期にある子どもたちには十分な睡眠必要です。塾通いも良いですがそれによって睡眠時間が少なくなってしまうようなら、その効果も半減です。
朝食は必ず食べる
グラフ12は文部科学省が行っている教育課程実施状況調査における朝食と学力の相関関係を示すグラフです。
「必ず食べる」と「たいてい食べる」を比べただけでも、実に一割近くの平均点の低下が見られるということです。
統計によれば「朝食を食べている子ほど学力は高い」のです。
子どもはすぐにお腹が空きます。なので朝食を食べないと午前中にお腹が空きすぎて集中力がなくなりますし、身体の成長にもよくありません。
パンではなくて、ご飯とおかずがいいらしいです。
テレビは一日一時間にする。
つまり、テレビの視聴時間が長く、睡眠や食事が不十分であることが学力低下を招いていたのですから、その逆をすればいいのです。
それで、私は土堂小学校に着任すると同時に保護者の方に集まっていただいて、二つのお願いをしました。ひとつは早寝早起き朝ご飯、もうひとつはテレビの視聴時間を当面二時間以内、できれば一時間以内にすること。
このふたつは、子どもたちの生活習慣を正しいものに導く上で、決定的な要素だからです。
テレビを長時間見ることは、それにより就寝時間も遅くなり、他のことに対する関心も低下し、あまり良いことはありません。
子どもにテレビを自由に見られる状態にすると、際限なく見続けるものです。
子ども部屋にテレビがある、なんてもっての他です。
テレビは許可制にして、見たい番組だけを録画して見せましょう。一日一時間以内が目標です。
「子どもらしい生活」は、学習にももっとも効果的な生活だった
上記の子どもの学力をUPさせる方法は、「子どもの生活をこのようにさせたら成績が上がった」というような「最初に方法ありき」で「考え出された方法」ではありません。
子どもの生活についての調査統計を見ると、成績の良い子と悪い子には、生活習慣の違いが如実にあらわれています。
それなら、成績の良い子の習慣を取り入れていけば他の子の成績も上がるだろう、という予測の元に、子どもの生活習慣を改善してみたら、やはり明確に成績の上昇が見られたのです。
日本には昔ながらの「子どもはこうあるべき」という精神論があります。
しかし、「学力第一」に考えても大人が考える「子どもらしい生活」というのは、結果を出せる正しい習慣だったのです。
「古い感性」も捨てたもんじゃありません。
この本は9年ほど前の本ですが、統計に基づいていて、「蔭山氏が実際に小学校で実践し結果を残したノウハウ」が書かれていて説得力抜群です。
そのノウハウとは何も特別な勉強法や、長時間学習などではありません。
子どもたちの学力上昇のみならず、子どもが心身ともに健康的に暮らすためには、「正しい生活習慣」を身につけることが重要なのです。
子どもが正しい生活習慣で暮らしていて不満を抱く親はいないでしょう。
ただ、子どもの生活習慣を変えることは大変です。必要なのは親の決意と根気でしょう。
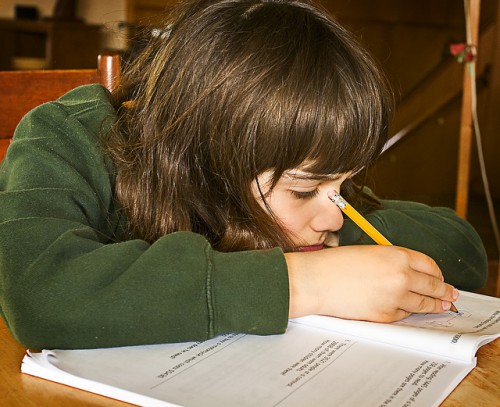



コメント