仕事を辞めるときの理由は、いろいろ取り繕っていても、本当のところはだいたい人間関係です。
大人ですら、いつも人間関係に頭を悩ませているのですから、経験の少ない子どもたちは、もっと人間関係に苦労していることでしょう。
わたしたちは、子どもたちに対してなにか有効なアドバイスが出来ているのでしょうか。
河出書房新社
売り上げランキング: 45,220
この本は、橋下氏ならではの「ぶっちゃけトーク」で、「真面目すぎる教師」や「キレイごと好きの親」が気づけない観点からの、「友だち論」を展開します。
友だちなんて大したもんじゃない
この本は中学生むけに書かれていますが、
下は小学生、上は高校生まで、人によっては大学生になっても、「いじめ」や「親友がいない」ということに子どもたちは悩んでいます。
親友がたくさんいて、いじめのない、理想的な学校生活が送れれば、それに越したことはありません。
しかし現実には、多くの子どもたちが友だちつきあいに悩み、一部の子どもは登校できなくなるくらい追いつめられてしまいます。
大人たちのアドバイスは「友だちをたくさん作りなさい」とか「積極的になれば友だちはできる」などという、「友情賛歌」的な建前論にとどまっています。
それでは、内気な子や、友だちとのトラブルを抱えた子たちの苦悩を和らげてあげることはできません。
そこで親としては美辞麗句ではなく、人生の先輩として子どもたちにいくらかでも救いとなる話をしてあげたいものです。
本書で橋下氏は独特の「友だち論」を展開します。
まず「友だちなんてたいしたもんじゃない」と喝破します。
そうではなくて、いっしょにいてしんどくなければ友だちなんだ、と考えてみませんか。
極端に言ってしまえば、友だちなんて、その程度のものにすぎません。
いっしょにいてイヤじゃなければ、もうじゅうぶんに友だちの条件の第一段階をクリアしています。君とその人は「友だちだ」と胸を張って断言できます。
「テレビやマンガなどに煽られ『友情は素晴らしい』という観念が社会に必要以上に固定化され、人間関係に器用じゃない子どもたちを悩ませ、苦しませているのでは?」
ということですね。
日本が豊かになり、精神的なものが重視されるようになってきています。
そして、時には過剰に「友情」「恋愛」というものがもてはやされ、それに無縁な人間は劣等感にさいなまれてしまいます。
今人気のマンガ「ワンピース」も、「仲間(友だち)は素晴らしい」というのがテーマです。他のマンガを見ても、「友情」「恋愛」を抜けば物語が成り立たないものばかりです。
この風潮は昔からで、例えば「一年生になったら一年生になったらともだち100人 できるかな♪」という歌があるように、友だちの数は多ければ多いほど、学校生活は楽しい(その子どもは素晴らしい)という価値判断が主流です。
親は子どもの学校生活充実度を、勉強と友人関係の二つで計ってしまうところがあります。
親が自分の子に「誰と仲が良いのか」とか「友だちは何人いるのか」などを、必要以上に詮索してしまうのもそのためです。
それは「親友」が何人もいるような環境は誰もが望んでいるでしょう。しかし、子どもにも個性があり、友だちの人数なんて個性により違うものでしょう。
それに大人が勝手に与えた「クラス」という制約もあります。
わたしの長女の小学校時代のことですが、休み時間に友だちと一緒にいることなく、いつも一人で校庭をうろうろしていたらしく、とても心配したものです。
しかし今思えば、本人は悩んでもいないし、つらいとは思っていないようでした。友だちを作ろうと努力したけど失敗したわけではなく、一人で行動したかっただけのようです。このように、友だちがいなくても案外本人は気にしていないケースもあるものです。
友だち関係はいつでもうまくいくとは限らないのに、大人のほうで「ふつうの友だち関係」のハードルをすごく高くしてしまっている状況があるんですね。
友だちなんてほんの一瞬のつきあい
自分には友だちがいないなんて悩んでしまうのは、僕に言わせれば、単に友だちの理想像が高いだけ。
わくわくして、喜びを分かち合って、安らぎの気持ちを与えてくれるような友だちだけを追い求めていると、現実とのギャップに苦しくなるばかりです。
繰り返し言いましょう。
いっしょにいられるだけで、友だちと言っていいのです。
たしかに、「仲の良い友だちを作れ」とか「友だちを大切にしろ」と、友だちつきあいを奨励して、楽しく学校生活を過ごさせてあげたいのが親心です。
ただ、その「前向き」な指導が、「友だちをうまく作れない」とか、「仲間はずれにされた」というような「素晴らしい友だち関係」に失敗したときに、子どもに必要以上に挫折感や絶望感を与えてしまっている面があります。
いま通っている学校、君が所属しているクラス、クラスの女子や男子、さらにそのなかのグループなんて、長い人生からすれば、ほんの一瞬の出会いにすぎない。いまだけの期限つきの関係です。
それなのに、悩んで悩んで命を落とすなんて、とんでもなく損です。
しかし、友だちは人生の本当の一部にすぎません。
友だちは、人間関係のなかではごくごく一部。割合でいえば本当にちょっとです。大人になって、「やっぱり中学時代に親友を作っておいたほうが良かった」と痛切に感じる大人なんて、まずいないと思ったほうがよいでしょう。
そう、公の場で子どもに向けてここまで言った人は、わたしは他に知りません。
ほとんどの子どもたちは、活動の場が家庭と学校に限られています。なので、学校の友だち関係がうまくいかず、居心地が悪くなると大人の想像以上に苦痛を覚えるものです。
子どもは時間の感覚があまりないので、この辛さがずっと続くかのように錯覚してしまいます。
もちろん、友だちとのうまくいかない原因を探り、対策をすることも大切です。でも、子どもでも一度こじれた関係は修復するのは難しいものです。
なので、まず問題に正面から向き合うことと、考えうる対策をすること。
そしてそれとは別に、橋下氏の言うように「今この一年は、君の人生からしたら一瞬でしかない」ということを、きちんと伝えないといけないのです。
クラスが変われば、また別の人間関係を作れる機会もあるでしょう。
自分の子どもが、友だち関係で悩んでると、親もかなり心配になるものです。でもそこで問題を突き詰めすぎたりでずに、
「友だちがいない?それは残念だけど、まあ大した問題じゃないよ。それより他に面白いことがあるよ」と、軸をずらした対応をすることも時には必要です。
問題を全部きれいに解決しようとし過ぎると、解決されない場合、子どもは余計につらくなってしまいます。
そして、トラブルなどで一度こじれた友だち関係は、修復するのが難しいものです。その場合、子どもの気分を楽にしてあげることにも気を配りましょう。
友だち関係がうまく行っているときには、「友だちを大切にしろ」と言い、うまくいかなくて悩んでいるときには、「もし、友だちとどうしてもうまくいかなくてもね、友だちなんてそんな大したもんじゃないんだよ」と、状況に応じて対応するべきです。「硬直した思想」は人を追い込みます。
大人には友だちはいない
大人って、そんなに友だちがいないものなんだ、親友といってもその程度の存在なんだーーー。
いま君がそう感じたとしたら、僕はこういいましょう。
大人にとって、一生の友だちにあたる存在、つまり、しょっちゅう会っている人間は友だちではなく、家族です。
君のお父さんやお母さんには、頻繁に会っている友だちはいますか。毎日のように会って話をしている友だちがいますか。きっといないと思います。
中学時代の友だち関係をいまでも続けている大人なんて、まずいない。
疑問に思うなら、お父さんやお母さんを含めて、君のまわりの大人たちに聞いてみるといい。「ねえ、お母さん、昔の友だちとどれくらい会っているの」と尋ねてみるといいと思います。
橋下氏は、小学校4年生まで暮らしていた東京と大阪で過ごした小学5年生時代の友人で、今でも付き合いのある友だちは皆無だそうです。
それ以降も、大学時代まで入れても、中学時代の2人としか、友だち関係は続いていないと。
余人なら知らず、弁護士や知事になった橋下氏のような人でさえ、大学以前の友だちは二人だけです。たしかイチロー選手も「本当の友だちは二人」とか言っていたような。
ダウンタウンの松本さんも、「友だちって対等な関係なんやろ、そしたら浜田しかおれへんなぁ」というようなことを言っていました。
あの世界の坂本さんも・・・
よく新聞とかで、エライ企業人とかの
昔話しで友達の大切さ、なんて書いてありますよね。
ぼく、あんなの信じられない。
坂本龍一 「現在友達と言える人はほとんどいない」
実は、というか、秘密でもなんでもないですけど、わたしも18歳で茨城から東京に出てきましたが、茨城時代の友人で今もつきあっている人は一人もいません。
ドラマとかではよくありますよね、田舎の幼馴染数人が、大人になってもつきあっていて、なにかあるとすぐにみんなで集まる、みたいな・・・。
まあ、そういう関係を保っている人もいるんでしょうし、少し憧れるような気もしますが、過去の友人とはほとんどつきあっていない人もたくさんいるようです。
通常「昔の友人とは一人もつきあっていない」とは言いにくいもんですが、坂本さんの後だと堂々と言えますね(笑)
そう、今わたしに友だちがいないのは、性格が悪いからではなくて、大人になったからです・・・と、視野を広く持ちましょう。
「親友をたくさん作れ」なんて、自分でも現在は出来ていないことを、あまり子どもにプレッシャーをかけてはいけません。
一つの事象も、捉え方しだいで前向きになれる、ということを子どもにも教えてあげたいですね。
親の「善意」が「苦しみ」に
「14歳の世渡り術」という副題があるように、この本は中学生むけに書かれています。
上記にとり上げた内容の他にも、具体的な「友だち対処法」が盛りだくさんです。
そのエッセンスは、小学生や高校生、大学生にすら通用するでしょう。とくに小学生には、親が要点を読み聞かせてあげると良いと思います。
「今がつらくても、クラス替えまで我慢すれば解放される」というような見方も、「子供もすでにわかっている」と思いこまずに教えてあげることが重要です。
友人関係にしろ勉強にしろ、親と言うのは「自分が出来たから」と言って、子どもにも同じやり方や成果を求め、子供の人格を認めない傾向があります。
もちろん、努力をさせるのは良いことですが、よく子どもを観察し子どもの限界や向き不向きを把握して、無理難題やプレッシャーをかけすぎないようにすることが大切です。
友だちの数も勉強のできぐあいも、個人によって違います。親と子どもが同じようにできるわけではありません。
親の「子どもに良い体験をさせたい」という思いが子供を追い込むことが往々にしてあります。
日本は素晴らしいことがたくさんある国だと思いますが、子ども社会のある種の息苦しさ、学校の治外法権化は、一部の子どもたちを苦しめていることは、今も昔もかわりません。
橋下氏の政治的主張やポジションに対する賛否はあるでしょうが、子どもが友だち関係に悩んだら、ぜひ読ませてあげてください。
その子の抱えた問題は簡単には解決しないでしょうが、気持ちはかなり楽になることでしょう。
友だちに「さようなら」されるのはつらいことですが、人間関係はおのずと変わっていくものだから、もがいてもしかたがない。
相手が距離を置きたいのなら、そうさせましょう。そして、君が友だち「さようなら」をするときは、相手がもがいたとしても悪くいったりせず、そのまま距離を置けばいい。
「さようなら」を告げるとき、「さようなら」を告げられるとき。
どちらにおいても、自然の流れに任せるのが一番です。


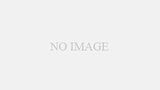
コメント